- 「自分の治療方針は、本当にこのままで良いのだろうか…」
- 「患者さん一人ひとりに合ったリハビリプログラムが組めない」
- 「勉強の必要性は感じるけど、何から手をつければいいか分からない」
理学療法士として働き始めた新人のあなたは、このような悩みを抱えていませんか?一つでも当てはまるなら、その悩みは、成長したいと願う新人理学療法士であれば誰でも通る道です。
学校で学んだ知識と、多様な背景を持つ患者さんと向き合う臨床現場との間には、誰しもが感じるギャップがあります。大切なのは、その不安を成長に変える「正しい勉強法」を知ることです。
この記事では、17年の臨床経験を持つ理学療法士が、明日からすぐに実践できる具体的な5つの勉強方法を分かりやすく解説します。さらに「頼られる理学療法士」になるための3年目までの目標やより効率良く学習するためのオンラインサービスも紹介します。
- 明日から実践できる勉強方法が理解できる
- 限られた時間の中で、効率的に勉強を進めるコツが身に付く
- 3年目までにどのように成長したらいいのか、その道筋が明確になる
日々の臨床に自信を持って向き合えるように、一緒に学びましょう。
新人理学療法士が直面する「3つの壁」

多くの新人理学療法士が、同じような壁にぶつかります。主な壁は、以下の3つです。
- 治療方針に自信が持てない
- 個別性のあるリハビリプログラムが作成できない
- 勉強の優先順位がわからない
治療方針に自信が持てない
- 「この評価は正しいのだろうか?」
- 「もっと効果的なアプローチがあるのではないか?」
教科書で見た通りの症例は、臨床現場にはほとんど存在しません。患者さん一人ひとりが、異なる身体的特徴や合併症、生活環境を抱えています。
知識としては分かっていても、目の前の患者さんにどう応用すれば最善なのか、判断に迷うのは当然です。経験豊富な先輩の治療を見るたびに、自分との差を感じて焦ってしまう。この不安は、多くの新人理学療法士が経験する成長の過程です。
大切なのは、不安を解消するために行動することです。
個別性のあるリハビリプログラムが作成できない
効果的なリハビリ計画は、疾患の知識だけで作ることはできません。その理由は、私たちは疾患ではなく「一人の人間」と向き合っているからです。疾患以外にも、以下のような項目も考慮する必要があります。
- 患者さんの年齢や体力、ADL(日常生活動作)のレベル
- 自宅の構造や家族構成といった生活環境
- 心の状態やリハビリへのモチベーション
- 仕事や趣味などの社会的背景
例えば、同じ脳卒中の患者さんでも、70代で一人暮らしの方と、40代で職場復帰を目指す方とでは、リハビリの目標もアプローチも異なります。経験が少ないうちは、どうしてもマニュアル的なメニューに偏ってしまい「個別性」を出せないことにもどかしさを感じることもあります。
勉強の優先順位が分からない
「勉強の必要性は痛感しているけれど、具体的に何から手をつければ良いのか分からない」
新人理学療法士に多くある悩みの一つです。日々の業務や計画書作成に追われる中で、学習の優先順位を見失いがちになります。解剖学や運動学、生理学といった基礎分野から、疾患別の専門的なアプローチまで、理学療法士が学ぶべき範囲は広いです。
やるべきことが多く「勉強しなくては」という焦りだけが強く、いざ参考書を開いても内容が頭に入ってこない、という悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。
明日から実践可能!新人理学療法士におすすめの5つの勉強法

新人時代に感じる不安や悩みを解消するためには、日々の臨床と学習を結びつけることが重要です。新人理学療法士におすすめの勉強方法は、以下の5つあります。
- 担当症例から学ぶ
- 基礎医学を固める
- 触診技術を磨く
- 先輩や同僚から学ぶ
- アウトプットして知識を定着させる
担当症例から学ぶ
最も効果的で実践的な勉強法は、目の前の患者さんから学ぶことです。臨床現場で生まれる「なぜ、この症状が?」「なぜ、この治療で?」という疑問は、何より強い学習動機になります。
教科書を1ページ目から読むよりも「今、知りたいこと」を深掘りする方が、知識は定着します。参考までに、具体的な実践方法を以下に記載します。
- 担当患者さんを決める
まずは一人の患者さんに絞る - 疑問を書き出す
評価や治療で感じた「なぜ?」をメモする(例:「なぜ肩の痛みが取れないのか?」) - 基礎に立ち返る
疑問に関連する解剖学・運動学の教科書を開き、構造と機能を確認する - 専門書・論文で裏付け
治療法の選択理由や病態の解釈について、より専門的な書籍や論文で根拠を探す
「臨床の疑問 → 基礎知識を確認 → 専門書や論文で裏付け」というサイクルが定着すると、成長スピードがグッと上がります。
基礎医学を固める
理学療法には、さまざまな治療手技がありますが、解剖学や運動学、生理学といった基礎医学は、理学療法士の仕事における土台です。基礎医学がしっかりしていれば、新しい知識や技術も、その本質からスムーズに理解できます。
参考までに、私が実際にしている基礎医学の勉強方法を以下に記載します。
- アプリを活用する
スキマ時間に「ヒューマン・アナトミー・アトラス」を使用し、筋肉の走行を確認する - 書籍を読む
講習を開催しているような先生の書籍を読む - 就寝前に再確認
その日に学んだ知識を一つだけ確認する
治療するためには、問題点を抽出する必要がありますが、問題点を抽出するためには、正常を理解しておく必要があります。疾患の勉強をする前に、基礎である解剖学や運動学、生理学の勉強をしましょう。

外部研修では、ある程度の解剖学や運動学、生理学の知識があることが前提として行われます。基礎知識の理解がないと、外部研修で十分な知識や技術が得られないこともあるため、しっかり基礎を固めましょう。
触診技術を磨く
どれだけ豊富な知識を持っていても、筋肉や骨を正確に触察できなければ、評価の精度は上がらず、治療効果も半減してしまいます。触診技術を向上させる方法は、以下の2つです。
- 触診の専門書を見ながら、自分の体で確認する
- 同僚や先輩にお願いして、フィードバックをもらう
触診の圧や角度は、フィードバックをもらい、直接指導を受けた方が上達します。勤務先にエコーがあれば、自分が触れている組織が画面に映し出されるため、活用しましょう。
先輩・同僚から学ぶ
一人での学習は、場合によって視野を狭めてしまいます。成長するためには、他者の視点、特に経験豊富な先輩や、同じ目線で悩みを共有できる同僚からの学びが不可欠です。先輩の治療を見学することがあれば、以下のポイントに注意して見学しましょう。
- 患者さんにどのような声かけをしているか
- 触れる時の手の使い方はどうか
- 治療全体の流れ(時間の使い方)
- どのような手技を用いているか
先輩に「どこに注目し、なぜその評価を選んだのか」など聞きましょう。自分の意見も先輩に伝えて、自分との違いを比較することが重要です。
同期は同じ悩みを持つ同僚です。お互いに担当症例について情報交換したり、触診の練習をしたりする時間を作り、ともに成長していきましょう。
アウトプットして知識を定着させる
「分かる」と「できる」には大きな差があります。学んだ知識を本当に自分のものにするには、インプットだけではなく、アウトプットが不可欠です。学んだことを同僚や先輩に伝えたり、患者さんに使用したりすることが効果的なアウトプットになります。
院内勉強会で発表できる機会があるのであれば、積極的に立候補しましょう。最初は失敗するかもしれませんが、失敗しても大丈夫です。「失敗は成功のもと」という言葉があるように、失敗しないと成功しません。
成功への近道は、失敗を最速でして学ぶことです。失敗を恐れず、挑戦しましょう。
忙しい新人でも続けられる時間術

「勉強の重要性は分かっているけど、どうしても時間がない…」
多くの新人理学療法士が抱える悩みです。しかし、時間は「作る」もの。日々の習慣を少し見直すだけで、学習時間は確実に確保できます。学習時間を生み出す方法は、主に以下の3つです。
- 朝活で「15~30分」を確保する
- スキマ時間を活用する
- やらないことを決める
朝活で「15~30分」を確保する
朝活がおすすめな理由は、一日のうちで最も脳がクリアな状態で、誰にも邪魔されずに集中できるからです。いつもより15〜30分早起きし、その時間を勉強に充てる習慣をつけましょう。「朝に勉強できた」という達成感が、その日一日のモチベーションにも繋がります。

朝どうしても起きられないという方は、職場にいつもより10分早く着くようにするのもおすすめです。私が実践している方法ですが、10分で5日間続けられれば50分の学習時間になります。10分でも結構本は読めますよ。
スキマ時間を活用する
通勤電車や昼休みの時間、患者さんを待つ数分間。こうした短い「スキマ時間」を合計すると、一日で意外と長い時間になります。スマートフォンに解剖学アプリを入れたり、読みたい論文のPDFを保存しておいたりと、スキマ時間にサッと取り組める学習ツールを準備しておくのがコツです。

文献検索にかける時間がない場合は、NotebookLMがおすすめです。活用方法に関しては、インスタの記事を参考にしてください。アプリもあるので、ぜひ活用しましょう。
やらないことを決める
時間を作り出すには「引き算」の発想も重要です。目的もなくSNSを眺める時間、何となくテレビを見ている時間。こうした時間を意識的に減らすだけで、まとまった学習時間を生み出せます。
例えば、1日30分だけ見直せば、1年間で182時間もの学習時間を確保できます。
☟時間管理術に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事に詳しく書いています☟
学習効率を上げるテクニック
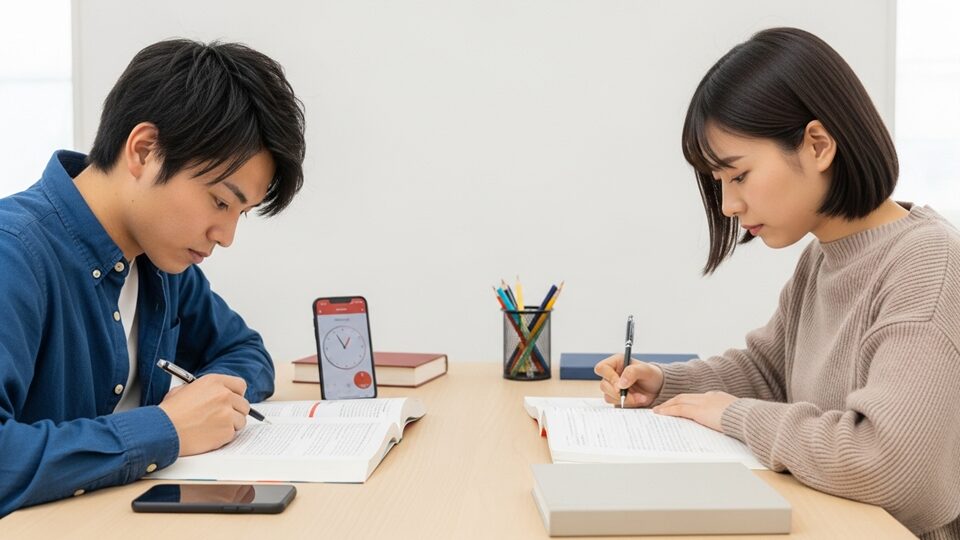
学習するなら、その学習効果を上げたいですよね。ここでは、学習効率を上げるテクニックを2つ紹介します。
アクティブリコール
これは、「読む」ことよりも「思い出す」ことを重視する学習法です。参考書を読んだ後、一度本を閉じて「何が書いてあったか?」を紙に書き出してみましょう。この「思い出す」という能動的な作業が、記憶の定着率を飛躍的に高めることが科学的に証明されています。
(参考:The Critical Importance of Retrieval for Learning)
ポモドーロ・テクニック
人間の集中力は、長くは続きません。この特性を利用したのがポモドーロ・テクニックです。「25分集中して勉強し、5分休憩する」というサイクルを繰り返すことで、高い集中力を維持したまま、長時間学習に取り組むことができます。スマートフォンのタイマーアプリで簡単に実践可能です。
ポモドーロ・テクニックでは、作業のキリが良いかどうかに関わらず、タイマーが鳴ったら強制的に中断します。これが、次の作業への意欲を高めるという心理効果になります。
燃え尽きずにモチベーションを維持する3つの方法

最初はやる気があっても、継続するのは難しいです。ここでは、モチベーションを維持する方法を3つ紹介します。
小さな目標で成功体験を積む
「3ヶ月で解剖学をマスターする」といった大きな目標は挫折しやすいです。「今日は三角筋の起始・停止を覚える」というように、確実に達成できる小さな目標を毎日設定しましょう。小さな成功体験の積み重ねが、学習を継続する力になります。
同僚との繋がりを大切にする
一人で頑張り続けるのは大変です。同期と定期的に情報交換をしたり、悩みを相談したりする関係を築きましょう。同僚の存在は、困難な時期を乗り越えるための支えになります。
休息をしっかりとる
最も重要なのは、十分な睡眠です。睡眠中に脳は記憶を整理・定着させます。心身が健康でなければ、質の高い学習はできません。休日には意識的に仕事や勉強から離れ、リフレッシュする時間も大切にしてください。
スマホを半日〜1日使用せずに、海や川、山など自然を楽しむのもおすすめです。
3年で一人前に!3年目までの目標設定

「いつまでに、何ができるようになればいいのだろう?」という不安がある新人理学療法士も多いと思います。ここでは、入職後3年間の標準的な目標を解説します。あくまで目安であるため、参考程度にしてください。就職先にキャリアパスがある場合は確認しておきましょう。
1年目:基礎固めと臨床への適応
目標例:先輩の助言を得ながら、基本的な評価・治療が一通りできる
一年目は、学生時代の知識を臨床現場で使えるようにする重要な時期です。担当することの多い疾患の病態を深く理解し、基本的な評価手技(ROM、MMTなど)を実施できるようになりましょう。
SOAP形式でのカルテ記載を習得し、日本理学療法士協会の「前期研修」を受講することも目標の一つです。
2年目:応用力と治療の幅を広げる
目標例:さまざまな症例に対応でき、治療の引き出しが増える
基本的な業務に慣れ、より応用的な視点が求められる時期です。複数の治療アプローチを学び、患者さんの状態に合わせて使い分ける能力を養います。後輩への指導を通じて自分の知識を再整理したり、院内の勉強会で発表に挑戦したりすることも、大きな成長に繋がります。
3年目:専門性の方向性を見つける
目標例:自立した理学療法士として、自分の強み・専門性を意識し始める
一人前のセラピストとして、複雑な症例にも対応できる力が求められます。この頃には、自分が特に興味を持てる分野(整形外科、スポーツ、神経系など)が見えてくることが多いです。興味のある分野の研修会に積極的に参加し、認定理学療法士などの資格取得も視野に入れ、将来のキャリアパスを考えましょう。
独学に限界を感じたら?おすすめオンライン学習3選

日々の自己学習や職場研修だけでは物足りない。もっと体系的に、効率的に学びたい方は、オンライン学習サービスがおすすめです。ここでは、オンライン学習サービスを3つ紹介します。
リハノメ
- 基礎から応用まで体系的に学びたい
- 新人向けの教育プログラムを求めている
- 講師の経験を基に話す内容を聞きたい
リハノメは、「何から学べばいいか」という新人理学療法士の悩みに、体系立てられたカリキュラムで応えてくれます。疾患別セミナーから実技動画まで幅広く網羅しており、新人理学療法士が最初に検討すべきオンライン学習サービスです。
毎月20本以上の動画が配信され、1本の動画が20~30分程度であるため、スキマ時間を活用して学べます。リハノメはアプリからダウンロードが可能であるため、オフラインで再生できます。
リハノメの料金は、以下のとおりです。
| プラン | 1か月見放題 | 6か月見放題 | 12か月見放題 | 24か月見放題 |
| 料金(1か月あたり) | 3,080円 | 2,772円 | 2,566円 | 2,181円 |
初月は980円(1か月)でお試しできます。理学療法士協会の会員であれば、クラブオフキャンペーンを使用すれば、上記料金から20%オフになります。今回紹介する中では、リハノメが一番安いです。

私も利用していますが、動画時間が短いことにメリットを感じています。入浴時間や食器洗いなど「ながら時間」で学習できます。事前にダウンロードしていれば、オフラインで再生可能であるため、余計な通信料もかかりません。
リハデミー
- リアルタイムで講師に質問がしたい
- 最新の論文情報などを効率よく得たい
リハデミーは、動画だけではなく、コラム記事や論文紹介など、コンテンツのバラエティが豊富です。ライブ配信セミナーがあり「その場で質問できる」のが特徴です。配信後には「アーカイブ動画」として視聴できます。
難易度も基礎的なものから応用・症例系まで揃えており「臨床経験が浅い人」「これから学びを広げて行きたい人」に対応しています。
リハデミーの料金は、以下のとおりです。
| プラン | プレミアム | スタンダード | フリー |
| 料金(1か月あたり) | 11,000円 <年払いの場合> 3,300円/月 39,600円/年 ※ 初年度のみ | 2,200円 | 無料 |
プレミアム会員は年間132,000円かかりますが、初年度は70%オフの39,600円で利用できます。リハノメと違い、プランによって利用できるコンテンツに制限があります。フリー会員は、セミナー・アーカイブ動画を購入した際、復習用動画を見るためのプランです。

私はフリー会員に登録中です。フリー会員になると、セミナーの案内が定期的にメールで届きます。気になるセミナーがあれば単発で購入して学習しています。
UGOITA
- 動作分析の視点を身に付けたい
- 評価から治療へのつなげ方を実践的に学びたい
- 実際の症例動画を通して臨床推論を学びたい
UGOITAは『運動と医学の出版社』が運営する治療家向けのオンライン学習サービスです。『本気で変わりたい治療家のためのサブスク』をキャッチコピーとしており、動きと痛みを治せるセラピストを目指すことがコンセプトになっています。
座学よりも「実際の患者さんのどんな変化を観察するか」を重視した内容であり、新人理学療法士が現場でつまづきやすい評価の具体性を学びやすい構成です。理学療法士の園部俊晴氏をはじめ、臨床現場で豊富な経験を持つ講師陣が多数登壇します。
UGOITAの料金は、以下のとおりです。
| プラン | ブロンズ | シルバー | ゴールド |
| 料金(1か月あたり) | 3,300円 | 5,500円 | 8,800円 |
リハノメやリハデミーと比較すると、月額料金は高めです。その分、より臨床に即した内容となっています。
『運動と医学の出版社』はYouTubeも運用しています。園部俊晴氏の考え方を知りたい方は、YouTubeを確認しましょう。YouTubeチャンネルでも質の高い情報が発信されており、こちらも参考になります。

個人的な見解ですが、リハノメやリハデミーと比較すると、基礎知識が理解できている必要があると感じます。
園部俊晴氏は多くの書籍を出版されていますが「園部俊晴の臨床『膝関節』」はおすすめです。エビデンスベースよりも、これまでの臨床経験をもとにした知識や評価、治療技術が惜しみなく解説されています。
まとめ:焦らず、自分のペースで成長しよう
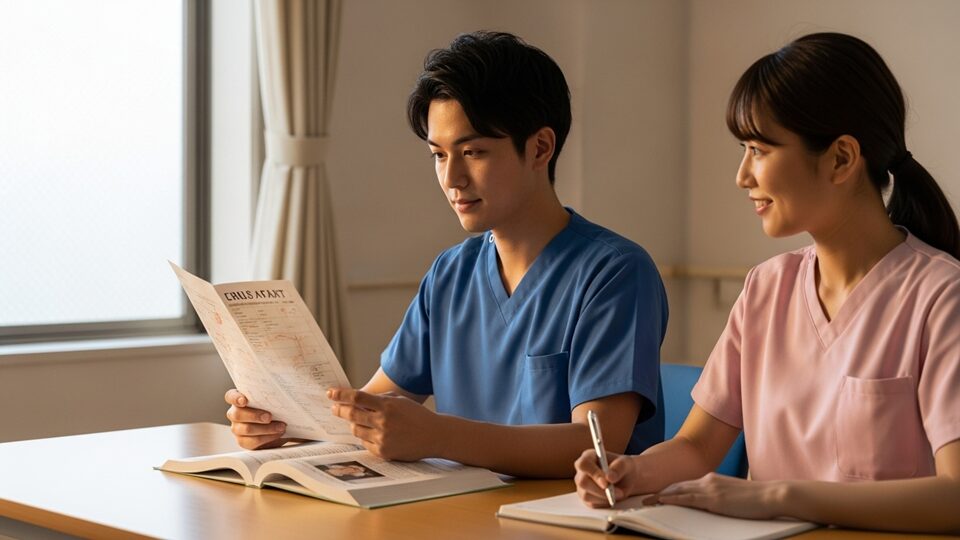
最後に、この記事の重要なポイントをまとめました。
- 担当症例から学ぶ
- 基礎医学を固める
- 触診技術を磨く
- 先輩・同僚から学ぶ
- アウトプットして知識を定着させる
新人時代の学習に、正解はありません。大切なのは、自分に合った方法を見つけ、焦らず、昨日より一歩でも前に進むことです。
臨床現場での小さな「なぜ?」を大切にし、一つひとつ丁寧に学んでいけば、その積み重ねが、3年後、5年後には確実に成長し、患者さんから信頼される理学療法士になれます。
まずは、この記事で紹介した5つの勉強法の中から、一つだけ選んで明日から実践してみてください。おすすめは「担当症例から学ぶ」です。明日担当する患者さんの疾患について、教科書を10分だけ開いてみる。それだけで、臨床の見え方が変わるはずです。
もし、独学や職場研修だけでは物足りない、もっと効率的に成長したいと感じたら、オンライン学習サービスの活用を検討しましょう。今回紹介した3つのサービスはどれも素晴らしいコンテンツです。ご自身に合ったサービスを見つけられるのがベストですが、実際に試してみないと分かりません。
新人理学療法士は、給料もそこまで高くないため、どれにしようか迷ったときは初月980円で開始できる「リハノメ」がおすすめです。リハノメは、新人向けの講座も充実しており、「何から学べばいいか分からない」という悩みに、体系的なカリキュラムで応えてくれます。
不安を解消するためには、行動するしかありません。一つからでもいいので取り組んで、理学療法士として成長していきましょう。
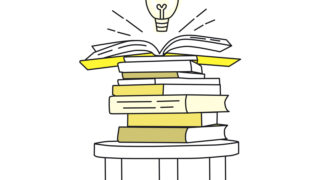

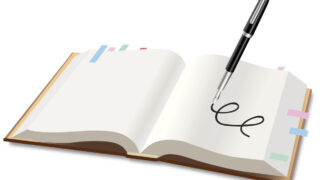

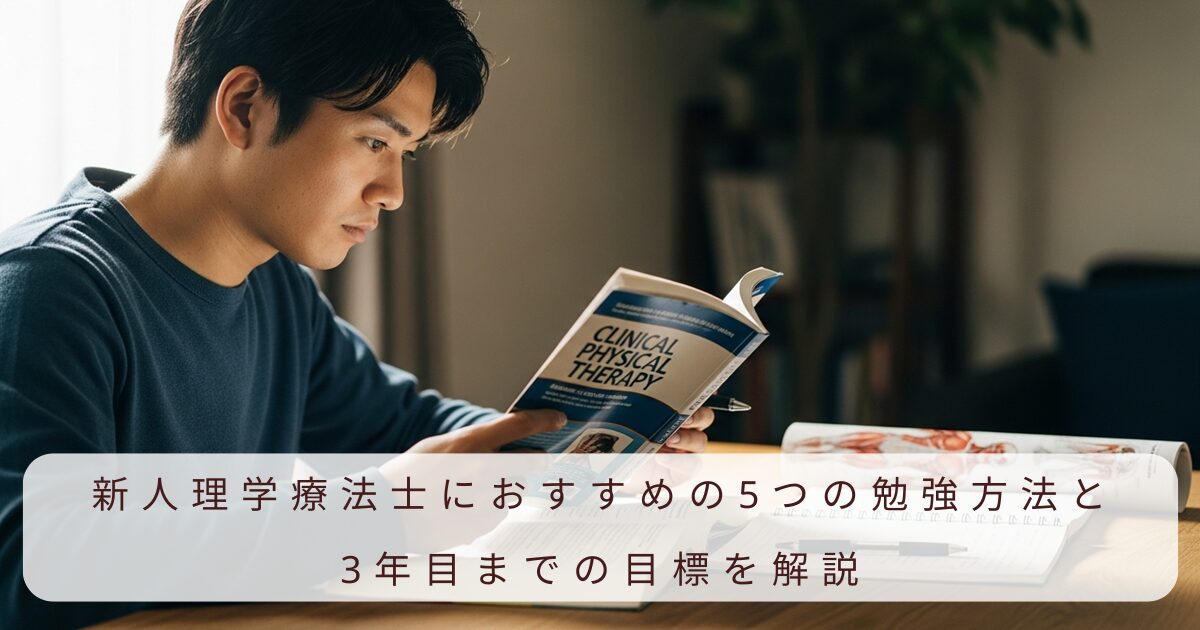




コメント